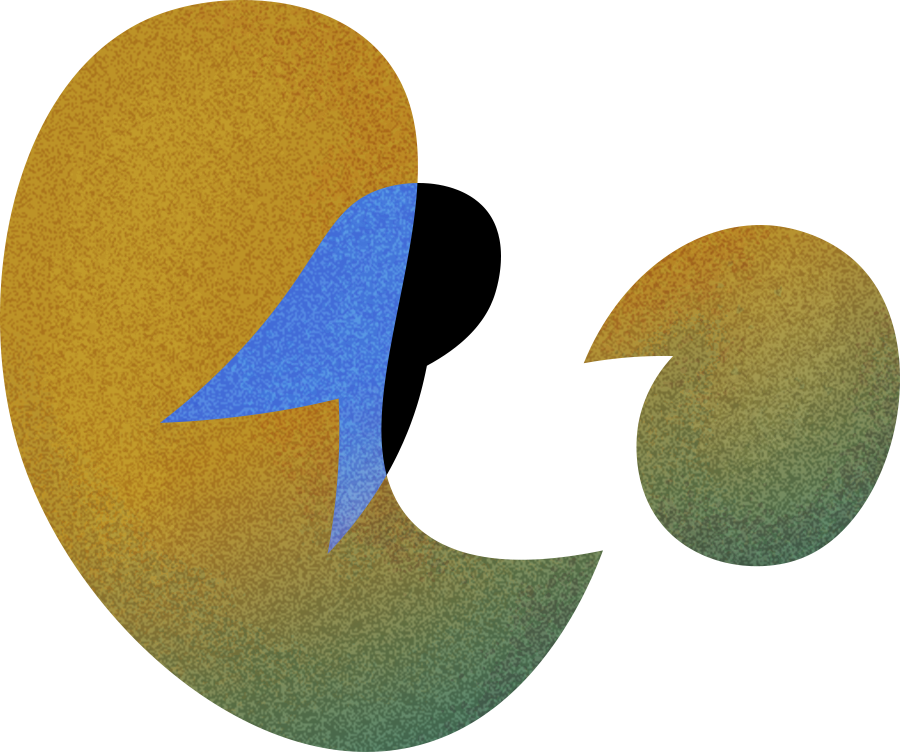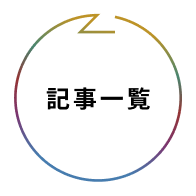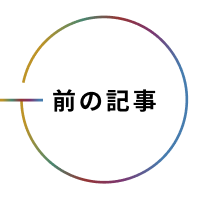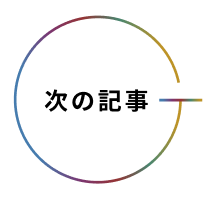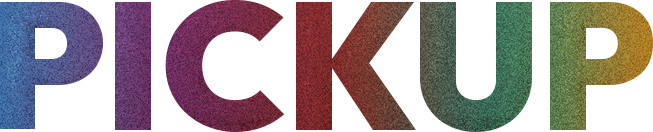🍛二皿目:身体で覚えた故郷・中国東北料理の味「紫金城、ゴウ・フォウファン」




「なじむ」をテーマに「生野のリアルな暮らし」に迫るインタビュー企画。第一弾では人生の浮かびあがる時も、沈んだ時も、日々変わらず私たちの胃袋を満たしてくれる「飲食業を営む方々」に話を聞いていきます。舌の肥えた彼らは、どんな味に出会ったとき「このまちになじんだ」と感じたのでしょうか?二皿目は、「生野の顔ともなっていた歴史ある中華料理店」を継いだ三代目ママのあの味です。
“ガチ中華”の名店「紫金城」引き継がれる

「紫金城」は生野の中でもとりわけファンの多い中華料理店だ。ザッと検索をかけただけでも、いくつかの食レポやブログを見つけることができる。その中身を見ていくと本場の味という意味の “ガチ中華”と称され、その無類の味を一度は味わうべく熱心なファンがわざわざ遠方から足を伸ばしている姿も散見された。
もちろん、足を運んでいるのは遠方の人たちだけでない。取材に伺った日も近隣に住んでいると思しき多くのお客さんで賑わっており、日本語・中国語・韓国語が飛び交っていた。ランチタイムのおしゃべりを楽しむ会社員もいれば、昼間からビールを傾けている年配者まで人種も年齢も、本当にさまざまである。
紫金城の歴史を紐解けば、韓国系中国人の初代シェフオーナー・岡村仁平と、瀋陽出身のチンホア(荊華)さんが日本で出会ったことがその始まりとなる。初代シェフオーナーは韓国の安東生まれだったものの、その父親は中国山東省出身。アメリカのレストランでの職務経験を経た後、日本で自身のルーツに根ざした韓国式中華料理と中国東北料理のレストランを日本でオープンさせるに至った。
名物はチャジャンミョン(韓国式の炸醤麺)。ルーツを考えれば、ここ生野はお店を持つにはこれ以上ない場所のように思える。当時、提供する料理の種類は200を超え、壁一面に貼られたメニューには中国語と、韓国語が並んでいたというが、時には二階でベトナム人が結婚式を挙げるなどこの街に移住してきた人々を受け止める坩堝となっていたことが伺える。

そんな前評判を聞いてお店に入ると、今の様子には戸惑う人も少なくないだろう。元々はお客さんだったという現在の紫金城のオーナー・ゴウ・フォウファン(郭鳳芳)さんがお店を継ぎ、店舗のリニューアルを行ったことでお店は随分ときれいになった。
パンデミックの影響もあり、ゴウさんの元で紫金城が営業を再開したのは2023年の8月と、つい最近のこと。1988年に開店。2008年に火災に見舞われたものの、現在の建物に移ってからもその人気は衰えることはなかった。こうした多くの人の支持を集めるお店を引き継ぐにはよっぽどの理由があったのかと思えば、話を聞いてみると案外そうでもないらしい。
「友達が紫金城のママ(チンホア)さんと長年知り合いで、以前から、お店を売るって話も何回かでてたから。懐かしい感じもある東北料理やし(それでお店を買うことにしました)。もともと料理が好き。難波でスナックもしてるんやけど、そこでも料理を出したりするんですよ」
中でもゴウさんが自信を持ってだせるのが「漬物」だ。まだ、紫金城では提供してはいないものの、新鮮な季節の野菜を中国式と日本式の味付けで漬けている。唐辛子の漬物など「それをちょっと干して、塩入れたら一回お湯をかける。一回お湯をかけたら、腐りにくい。また鍋に醤油とタレいれて、熱いままいれて」と、作り方を聞いているだけでもよだれが出てくる。「うちいいグラスで、安いお酒で、いい漬物、そういうファンのお客さんが多いねん」という言葉にも説得力がある。
一回ちょっと離れよって、故郷を

実は、ゴウさんがお店を引き継ぐ話は2年以上も前からあった話だという。
付け加えて、「運命ですよね、自然に流れ着いた」と朗らかに話しながら品のある笑いを見せるゴウさんだが、お店のオープンは「もう一度あの時に戻れるなら引き継ぐのは躊躇する」と語るほど一筋縄ではいかなかった。そもそもお店を引き継ぐといっても、前オーナー時代からの店長・山本さんを除いた全スタッフが退職をし、人材集めから始めなければいけなかったという。
「たまたま親友が知り合いのコックさんを二人探してくれて。それにスナックやっているとね、いろんな人が飛び込んでくるでしょ。勉強になります。このお店をやるときにも、アドバイスしてもらったり。商売してる人は、失敗の経験もたくさんあるし」
こうした周囲の人々に助けられながらなんとかお店をオープン。開店からわずか三ヶ月だが、すでにスタッフの人数は10人を超える。もともとが人気店であったがゆえに「こじんまり」とはスタートできなかったのだろうか、とそんな苦労が頭をよぎった。
早くもスタッフ全員がこの環境に慣れ「みんな仲良くてめっちゃいい感じ」だという。そして今、フロアには息子であるシーショウカ(石紹華)さんが立つ。日本で育ち、日本語も中国語も話せる彼は、厨房をつなぐ大事な役割を担っているのだ。

そんなゴウさんがまだ幼かったショウカさんを連れて日本に来たのは2007年の11月17日のこと(誕生日の3日前で覚えやすかったようで、日付まで即答)。一度、旅行で訪れたきりの日本にやってきたのは、深くは理由を語らなかったが前の夫との離婚がきっかけだった。
「一回ちょっと離れよって、故郷を。たまたま、友達の友達が日本にいてね。それで日本に来ました」
それまでゴウさんは、生まれ故郷であるロシアとの国境に面する黒竜江省でずっと暮らしていた。当時は日本語が話せたわけでもなく、いきなり国外で生活するのは大きなチャレンジのように思える。不安はなかったのだろうか?
「今、振り返れば親のおかげで。漢方薬の販売をしていたから、遠い街からいろいろな人が商売にやってきた。私、お父さんにずっと可愛がってもらって仕事に付いていったり、ご飯を食べるのもおつきあいしたり、ずっと側におったから、(知らない人と話したり、違う世界に飛び込むことは)恥ずかしいけど大丈夫。ただあの日の、気持ちは特別。とにかく、日本でお金を稼いでこの子にいい生活をさせてあげたい気持ちが強かった。怖いよりそっちの気持ちが強かった」
小さな頃から自然と胆力がついていたという話だが、幼い息子を一人抱えて異国で暮らしていくことのハードルはそれだけで乗り越えられるほど低いものではないはずだ。そうした経験と比較すれば、(もちろんゴウさん本人は大変だったとは言うものの)お店を一つ引き継ぐことは彼女にとっては難しいことではないのかもしれないと感じた。
中華料理と、中国東北料理はまったくの別物

日本へ来て、知人のツテをたどって最初に居を構えたのは今里だった。
その後、ゴウさんは清掃や居酒屋のアルバイト、韓国系のクラブなどさまざまな職種を経験した。そして、最終的には自身のスナックを持つにまで至ったものの、「自分のお店を持ちたい」と思ったことはあまりなく、あくまで「一つずつつながっていった」とはゴウさんの言だ。そしてその縁が今、紫金城にまで結びついた。
ゴウさんの紫金城でのポジションはあくまでオーナーであり、(仕込みはするものの)厨房には立たない。しかし料理が好きで、家でも創作料理をふるまう彼女のこだわりは、深い。今でこそまだメニューも前オーナー時代のものを使ってはいるが、少しずつそうしたこだわりをお店に反映している最中だ。
「例えばお皿、切り方、盛り合わせ。そうしたものを変えて、私はほんまの中国(東北)料理のような感じにしたいんです。同じ料理でも、材料の切り方一つで全然違う。例えば、空芯菜とかほうれん草とか炒め料理あるやん。大体みんな野菜を切ってから洗うことが多い。それは駄目。洗ってから切る。そうしたら水が入らない。炒め終わって、お客さんに運んだ時に、皿の底にちょっとだけ汁がある(のがおいしい)。切ってから洗うと、汁があふれるんよ」

ゴウさんのこうしたこだわりは時にシェフとのケンカのもとにもなったというが、目指すのはこの場所で自身のルーツとなっている中国東北料理を、“おいしく”提供していくこと。そのモチベーションの源泉には「気品のある料理を出したい」という強い想いがある。そしてそのために今、少しずつメニューを厳選していっているところだ。
「例えば(以前メニューには)春雨だけでもね、ニラ春雨とか五つくらい(バリエーションが)ある。ややこしい。北の料理だったらね、里芋のスパイスだとほんまはこれしかないねん。昔は貧乏だから、これしかないわけよ。(魚の)煮込みもね(全部)削った。例えば今夜、魚届くやん。きれいに洗ってすぐ(料理を)出せるように冷凍するね。そしたら煮込み料理出した時、新鮮じゃなくておいしくない」
強いこだわりは持つもののゴウさんはあくまで、こうした自身のスタンスを押し付けているわけではない。お客さんがどのように料理を食べているか、どこまで食べきれているか、食べにくそうにしていないか、そうした観察をずっとしていることが話を聞いていると伝わってくる。
加えて、従来のお客さんのためにこれまでの料理を急激に変えることなく、少しずつチューニングを重ねている。こうした料理への真摯な姿勢が伝わっていることは、オープン時には集客に苦戦したものの、今では客足が戻り、リピーターも増えつつあるということが証明しているはずだ。
お父さんの味、でない

そんな彼女の食へのこだわりがどのように形成されていったのかを知るには、黒竜江で暮らしていた子ども時代の生活にヒントがある。ゴウさん自身は都市部に住んでいたものの、父親の持つ長白山人参の栽培・加工場が自然豊かな山の中にあり、小さな頃からそこに毎日通っていたという。
「あの時の生活が楽しくて。山さくらんぼ、山モモ。イノシシ殺して食べたり。仕事終わったらね、みんなでご飯食べてたから畑もあるでしょ。にんにくの芽、きゅうり、野菜その場で採って食べる。農薬ない。そのまま食べるその味がおいしい」
山では鶏や豚も飼っており、お肉はしめたてで、さらに調理は窯焚きだ。そうした環境がゴウさんの舌を自然と肥えさせていったことは想像に難くない。こうした生活はゴウさんが16歳くらいになるまで続いたものの、都市開発とともに山が崩れ終止符が打たれた。今では、そのまま飲めていた山の水も飲めなくなってしまったと残念そうに教えてくれた。その後、生活の足場は街の方へと移っていくものの、山での贅沢な食体験は「味の濃い野菜を求めて、道の駅では形の崩れた野菜を買う」という現在の習慣にまでつながっている。

そんな彼女に「なじみの一皿」を聞いてみたところ、「まだ仕事が忙しくて生野では外であまり食事ができていないから」ということで、代わりに子どもの頃に食べていた「干し豆腐と青唐辛子の炒めもの」が思い出の味だと教えてくれた。
「本当に子どもの頃の味ね。うちのお父さんよく作ってくれた。でもこれ結構難しい。あんが多かったらだめ、少なくてもだめ。以前この店で出してた時、干し豆腐切ったあとそのまま使ってた。私になってから骨のスープでゆがいて柔らかくなってから炒める」
あわせて、自分でもおいしいとは思うものの、なぜかお父さんの味が完璧には再現できないのだということだ。話をしていたら、お父さんのことを思い出したのか、ゴウさんの目が少し遠くなったように感じたのは気のせいだっただろうか。楽しかった思い出とともにあるその味がどのようなものだったのか、ゴウさんが作った料理がその味と同じものであるのかはもはや私たちに知る術はない。ゴウさんの身体に馴染んだその味を、ただ楽しむだけである。
ゴウさんが自身のルーツである中国東北料理をとても大切にしていることは、「専門的な調理や料理の勉強はしたことがない」と言いながらも隅々まで配慮された調理プロセスや、食材へのこだわりが体現している。そうして生み出される一皿には、ゴウさんの身体に馴染んだずっと暮らしてきた市井の中国東北料理の旨味がギュッと濃縮されているに違いない。
前オーナー時代の紫金城は、日本人・韓国人・中国人だけでなく、ベトナム人やネパール人など実に多様な人々が出入りをしていた、ある種伝説的な店でもあった。そうした人々がこの街へなじんだ証として、紫金城の中国東北料理の味を身体で覚えるその日もそう遠くはなさそうだ。

| ★紫金城 住所:大阪府大阪市生野区新今里3丁目10−26 https://maps.app.goo.gl/2o49ZNaRAwaGNqNG8 営業時間: 10:00-23:00 定休日:なし |